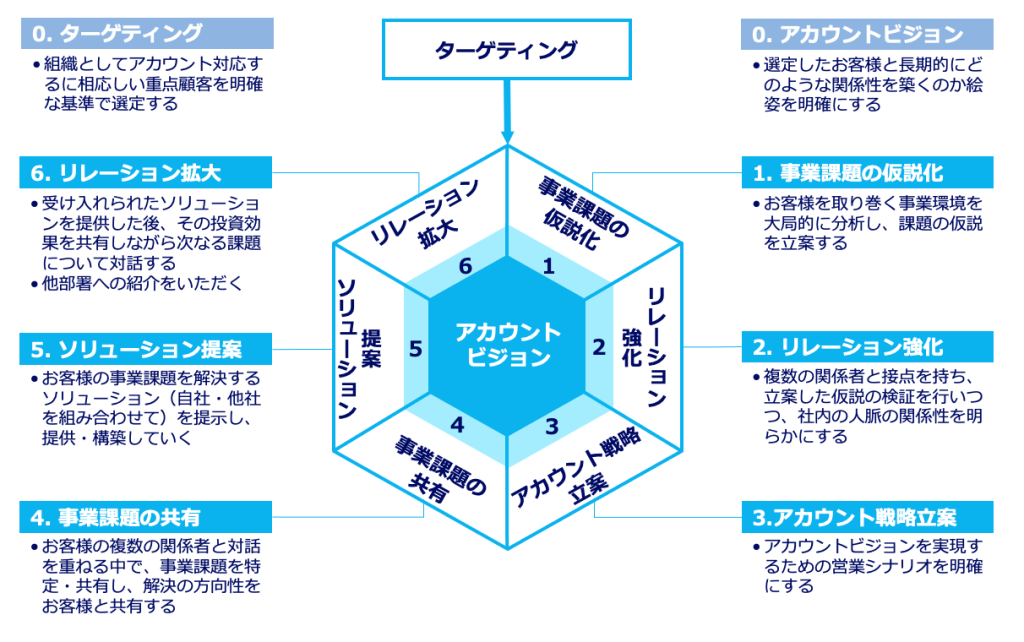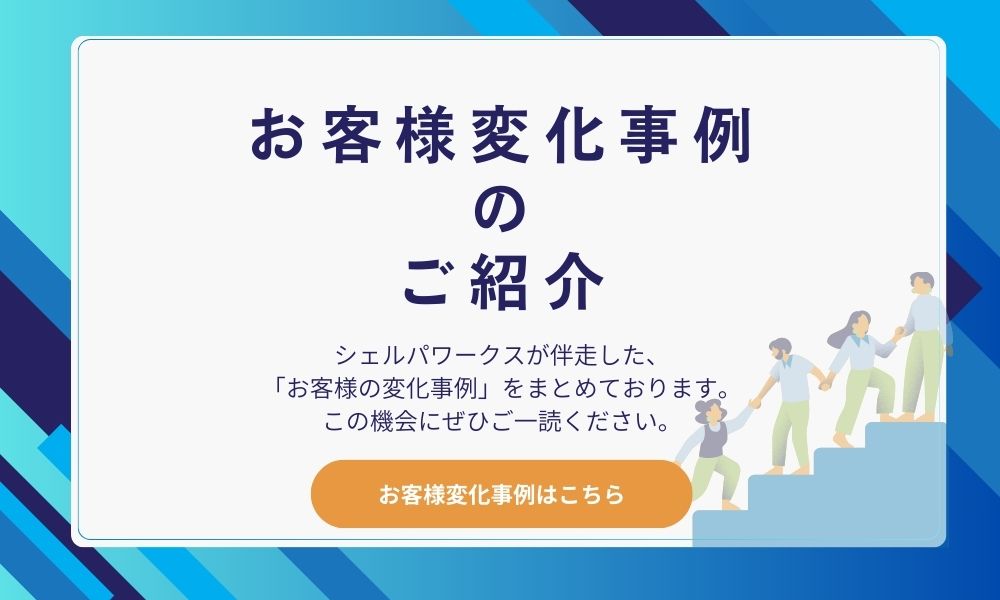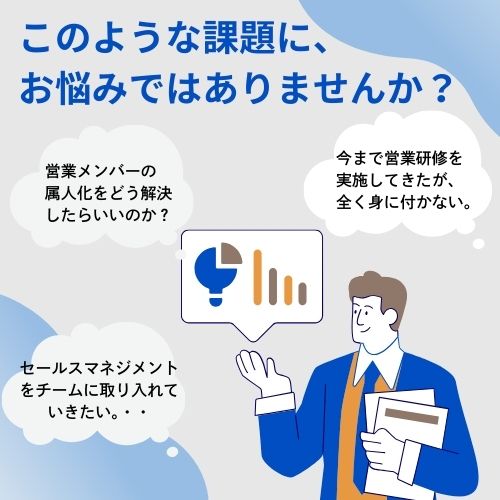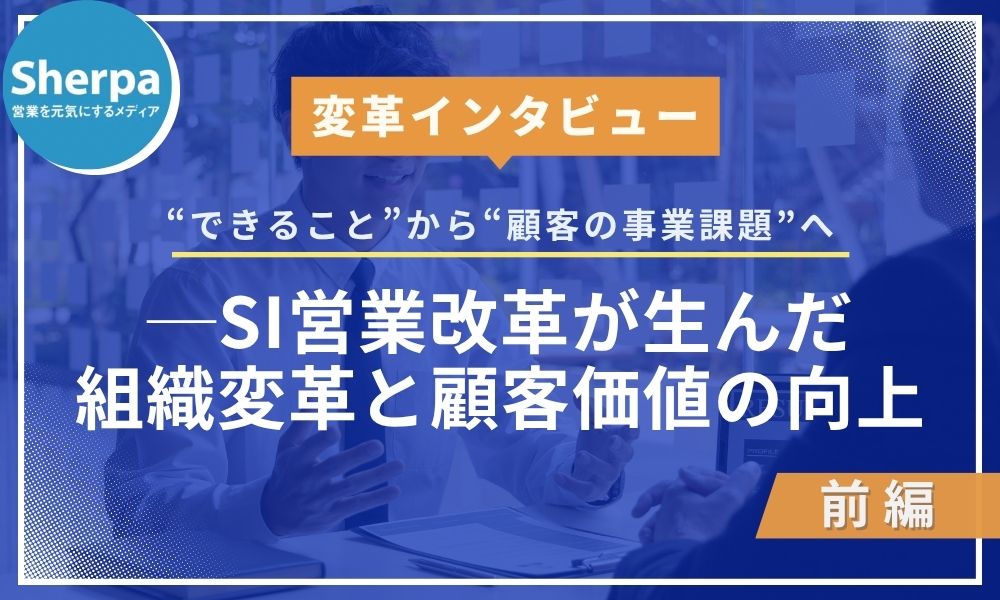
2025.10.14 (更新日:2025.10.16)
“できること”から“顧客の事業課題”へ──SI営業改革が生んだ組織変革と顧客価値の向上 前編
市場環境が加速度的に変化する中、従来の「自社の強み」だけに頼ったBtoB営業では、顧客の心をつかむことが難しくなっています。
本記事では、システムインテグレーターA社のソリューション推進部高橋部長にお話を伺います。変化する市場や顧客との関係の中で、実際の現場では何が起こっていたのか、営業スタイルの転換が必要なことを管理職として確信したきっかけについて明らかにします。
※本シリーズは、ある企業で実際に行われた営業変革の事例をもとに構成しています。登場人物や会社名は架空ですが、現場の葛藤、会話、そして変化のプロセスは、すべて実際の出来事から着想を得ています。
A社会社概要:
情報サービス業(情報処理サービス業)システムインテグレーター(SI)。
企業や組織が抱えるITニーズに対して、コンサルティングから設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して提供する事業者です。単にシステムを作るだけでなく、顧客の業務プロセスや経営課題を理解し、それを解決するためのIT活用を総合的に支援する役割を担うとされています。
SIのビジネスでは、深刻な人材不足と、それに関連する技術力・人材育成の停滞が大きな課題となっています。その背景には、AI・クラウドを始め新技術が次々に登場し、求められる知識やスキルが広範かつ変化のスピードが速いため、現場の人材が常にキャッチアップを強いられる状況があります。人材育成の負担が重く、十分なサポートが行き届かないことが離職や採用難につながり、人材不足がさらに加速するという悪循環が生じています。これは組織の競争力を削ぐだけでなく、経営リスクとしても顕在化しています。さらに、特定ベンダーへの依存による“ベンダーロックイン”が新たな課題として浮上しています。こうした背景から、業界全体として構造改革と新たな価値創出の両立が強く求められています。
目次
AI、クラウド化で変わる市場。仕様通りに納品しても、パートナーにはなれない
――当時の営業活動はどのような状況だったのでしょうか。
高橋部長:
「当時の私たちA社は、ある意味“優等生”でした。顧客から依頼された通りにシステムを設計し、仕様通りに作り、納期通りに納品する。それを正確に実行できることが、営業や技術の誇りでもあったんです。
ただ、時代は大きく変わり始めていました。IT業界はクラウド化とサブスクリプション型ビジネスの普及で、競争が一気に激化。海外ベンダーが参入し、価格競争は熾烈になり、技術優位だけでは選ばれなくなっていたんです。さらに顧客の事業環境も、AI活用、DXの推進や人材不足、サプライチェーンの混乱など、課題が複雑に絡み合うようになっていました。
従来型の“機能提案”や“製品スペックの説明”だけでは、顧客の経営層に刺さらない。彼らが求めているのは『御社の技術をどう事業成長に結びつけられるか』『どうすれば競争優位を築けるか』といった問いへの答えでした。私たちはそれに気づきながらも、日々の営業活動が支障なく回っていたために、“今まで通りの延長”から抜け出せていなかったんです。」
自社が変わらない間に環境は変わっていた~ 20年続いたやり方との決別
――転換を決断するきっかけは何だったのでしょう。
高橋部長:
「一番大きかったのは、ある年末の訪問です。長く取引しているお客様に『A社の担当は優秀。でも、それだけですよね』と言われました。笑顔の裏に、“このままでは選ばれ続けない”というメッセージが透けて見えて…。あの瞬間、胸に重石をのせられたような感覚になりました。」
――それはショックですね。ほかにもきっかけはありましたか。
高橋部長:
「ありました。些細なことなんですが、それが積み重なって確信に変わりました。
たとえば、提案の場で『これって御社にしかできないことなんですか?』と聞かれて答えに詰まったこと。技術的には優れているのに、“事業上の独自性”を語れなかった。
あるいは、競合に負けた後にお客様から『製品は遜色なかった。でも、あちらは我々の経営課題を踏まえて話をしていた』と耳打ちされたこともありました。
もっと小さな場面では、商談後に顧客が『このソリューションを入れると私たちの業務プロセスは楽になるんですかね?』と雑談的に言ったのに、うまく答えられなかったこともありました。たった一言だったのに、その一言に“顧客は製品導入の効果だけではなく、業務プロセス全体の変化で判断している”と気づかされたんです。
こうした出来事が一つ一つ積み重なって、私の中で、最終的に『顧客起点に立たなければ未来はない』と腹落ちしたんです。」
――今までと顧客が求めるものが変わってきたということでしょうか?
高橋部長:
「AIを用いた需要予測や顧客データ分析も当たり前になってきて、今まで以上に市場の変化のスピードが速くなってきているということはあるでしょうね。提案力とかコンサルティング力、傾聴力が大切とは今までも言われてきましたが、それ以上のものが求められる。お客様自身にも未来が分からなくなっているんじゃないかと思います。競合他社が顧客課題を深く分析したうえでの提案を出してくるのであれば、うちもそれ以上の力を付けて変わらなければ、勝ち残れないと思いました。」
板挟みと孤独感の中での葛藤
――その決断には社内から反発もあったのではないですか。
高橋部長:
「正直、相当ありました。『急にコンサルタントみたいなことをしろと言われても』『そういうのはうちには合いませんよ』とか、『うちは確実にいいものを作っているんだから、いずれ良さが分かります。余計なことをしないほうがいい』とか。若手の中には『自社製品の領域だけでもどんどん新しいことがでてきて大変なのに、どんなに勉強してもキリがないのではないですか』と言う者もいました。
本部からは“早く変えろ” “いつまでに”という強いプレッシャーがある。現場からは“やりたくない” “やるべきでない”という反発が返ってくる。その間に立つ私は、まさに板挟み。夜のデスクに一人で残り、窓に映る自分を見て“この孤独感に耐えられるだろうか”と自問したこともありました。それで検索して、ノウハウを持っていそうな会社を探していたのです。」