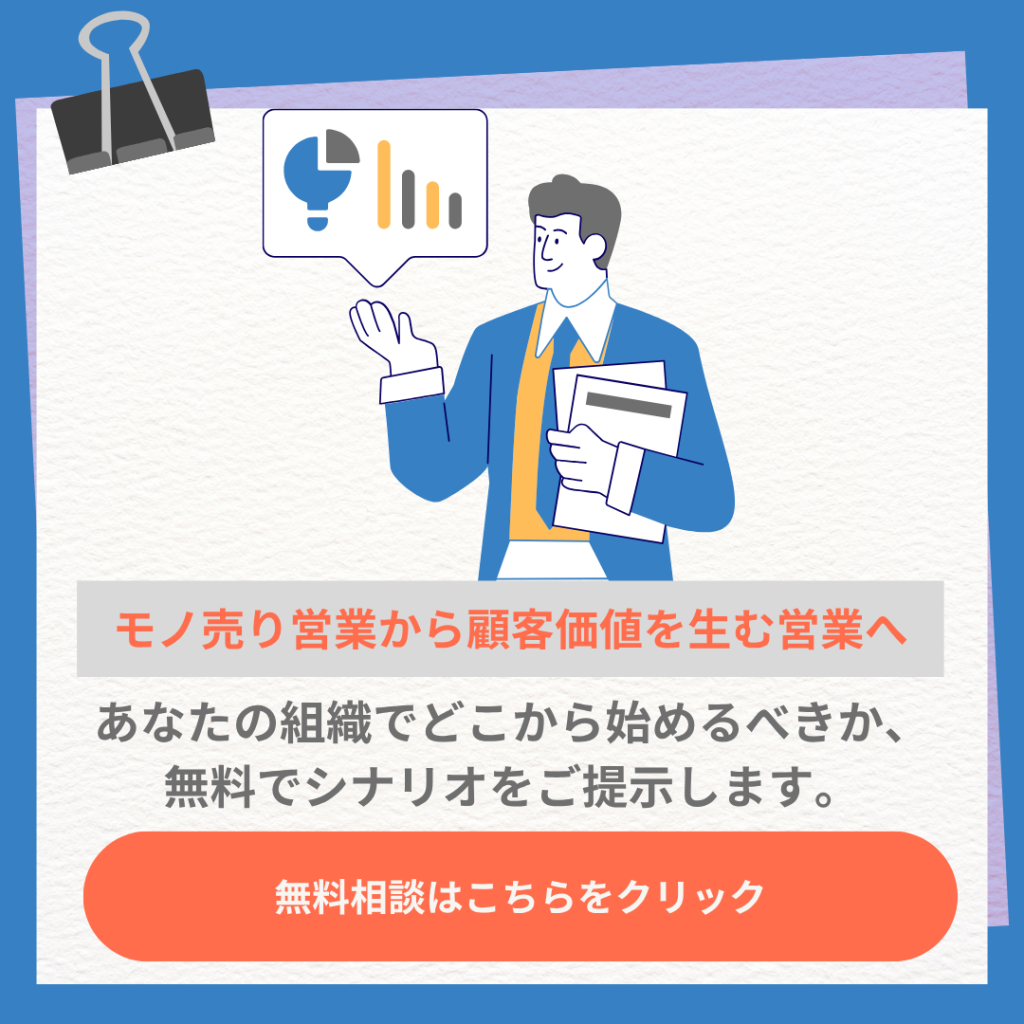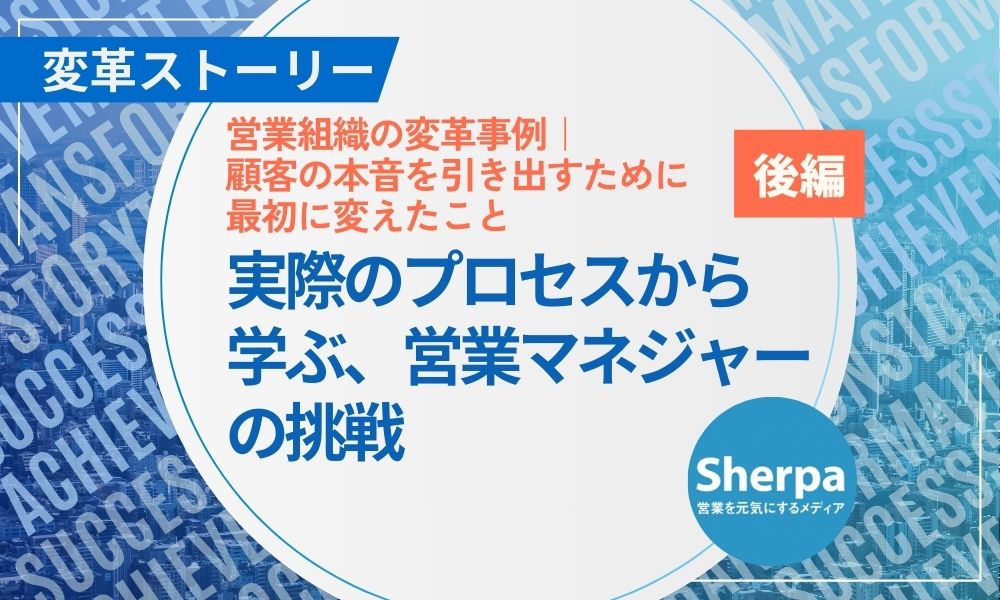
2025.09.25 (更新日:2025.10.10)
営業組織の変革事例|顧客の本音を引き出すために最初に変えたこと【後編】~実際のプロセスから学ぶ、営業マネジャーの挑戦~
営業組織が顧客の本音を引き出せず、価格交渉ばかりに終始してしまう──。本記事では老舗食品メーカーの営業チームが変革に踏み出した事例をもとに、営業会議や1on1面談を通じて“顧客と向き合う文化”を育てたプロセスを紹介します。
(注)本記事は、ある企業で実際に行われた営業変革の事例をもとに構成しています。
登場人物や会社名は架空ですが、現場の葛藤、会話、そして変化のプロセスは、すべて実際の出来事から着想を得ています。
目次
顧客に踏み込む営業が生まれ始めた
会議の在り方を変えたことで、若手もベテランも「顧客の困りごと」を聞き出す姿勢が芽生え始めた。現場での小さな一言が、商談の切り口を広げていることがわかる。
会議の空気が変わったことで、現場での行動にも微かな変化が見え始めていた。
若手営業の佐藤は、先週の会議で共有された「店長の人手不足の話」が頭から離れなかったという。
その日、彼は地方の郊外にあるファミリーレストランの厨房に立っていた。
いつもなら納品口で商品を手渡し、軽く挨拶を交わしてすぐに商談に移る。
だが、この日は違った。
忙しそうに動き回る店長に声をかけた。
「店長、この前の会議で話した人手不足の件、今はどんな状況ですか?」
店長は一瞬驚いた表情を見せ、それから手を止めた。
「いやあ…相変わらず厳しいよ。朝の仕込みだけでスタッフがバテてしまう。」
佐藤はさらに踏み込んだ。
「どの作業が一番大変なんですか?」
「カット野菜とソースの仕込みかな。特にソースは時間がかかるんだよ。」
その答えを聞いた瞬間、佐藤の頭に「会議で共有しよう」という考えが浮かんだ。
これまでなら聞き流してしまっていた話が、今ではチームに持ち帰るべき“情報”に変わっている。
宮坂も別の動きを感じ取っていた。
ベテランの高橋が商談の帰りに、「今日は商品の話をする前に、相手の困っていることを聞いてみた」と報告してきたのだ。
「そうしたら、原価高騰でメニューを変えるか迷っているって話をしてくれてね。
これ、うちの提案にも関わってくると思うんだ。」
その言葉に、宮坂は小さくうなずいた。
(少しずつだが、“顧客に踏み込む”営業が生まれ始めている──)
「困りごと」を聞くことで見えた現場
営業が顧客の課題を率直に尋ねることで、衛生管理基準やアレルギー対応など新しいニーズが顕在化。提案の幅が広がり、関係の深まりにつながっていった。
営業会議で「顧客の現場を聞く」ことを繰り返し意識してきた成果が、少しずつ形になっていた。
その変化は、若手とベテランを問わず、商談の冒頭のやり取りに表れ始めていた。
入社5年目の中堅営業・井上は、その日、取引先の中堅惣菜工場を訪れていた。
以前ならすぐに商品の紹介に入っていたが、この日は工場長との雑談から始めた。
「最近、現場はどうですか? 何か変わったことはありますか?」
工場長は、少し驚いたような表情を見せ、帽子の位置を直しながら答えた。
「実は、新しい衛生管理基準が来年から適用されるんだよ。それに対応するために、現場は大忙しだ。」
井上はさらに尋ねた。
「それはかなり負担が大きいんじゃないですか?」
「そうなんだ。特に調理工程の記録や管理方法を変えないといけなくてね。人手も足りないし、やりくりが大変だよ。」
井上は、会議の光景を思い出していた。
宮坂が言っていた、「相手の背景を聞くと、提案の切り口が変わる」という言葉だ。
この話は、商品の提案だけでなく、工程改善の相談にもつなげられるかもしれない──。
一方、ベテランの高橋も、同じように変化していた。
長年取引している給食事業者の担当者に、何気なくこう尋ねた。
「このところ、一番困っていることって何ですか?」
担当者は一瞬黙った後、机の上の資料を指さした。
「実はね、アレルギー対応メニューを増やさないといけなくて、仕入れ先の選定に困っているんだ。」
これまでなら、直接関係のない話として流してしまっていたかもしれない。
だが今は違う。
高橋は「うちでも対応可能な食材があるかもしれません」と返し、具体的な相談の約束を取り付けた。
宮坂はその報告を聞き、心の中で手応えを感じていた。
(“困りごと”を聞くことが、次の提案の入り口になる──これこそが、顧客に踏み込む一歩だ。)
大きな成果を生んだ一つの提案
若手営業が拾った「ソース仕込みの負担」という声から、開発部と連携して新商品を提案。結果として大口契約に結びついた成功事例が生まれた。
若手営業の佐藤は、ある商談で聞き出した情報をきっかけに、大きな一歩を踏み出すことになった。
それは、地方に数店舗を展開するファミリーレストランチェーンの厨房での会話だった。
「一番負担が大きい作業は、どの工程ですか?」
そう尋ねた佐藤に、店長は少し考えてから答えた。
「カット野菜とソースの仕込みだね。特にソースは手間がかかるんだよ。朝から仕込んで昼のピークに間に合わせるんだけど、スタッフの負担が大きい。」
その時、佐藤の中で何かがつながった。
(もしこの作業を短縮できる商品や方法を提案できれば…)
帰社後、佐藤はすぐに宮坂に相談した。
「店長がソース仕込みに時間がかかって困っているそうです。これ、開発部と一緒に何かできませんか?」
宮坂は即座に開発部門に連絡し、試作チームを招集した。
条件は二つ──現行の味を損なわないこと、そして仕込み時間を半分以下に短縮できること。
数週間後、試作品が完成した。
佐藤は開発担当とともに店舗を再訪し、試作品を使った調理実演を行った。
店長は試食しながら目を見開いた。
「これなら、朝の仕込み時間がかなり短縮できる。しかも味は変わらない。」
この提案はすぐに採用され、全店舗への導入が決まった。
結果として大口契約に繋がり、さらに店舗スタッフからも感謝の声が寄せられた。
後日、営業会議でこの事例が紹介されたとき、メンバーから自然と拍手が起こった。
宮坂はその光景を見ながら思った。
(“困りごと”を聞くことが、顧客と共に価値をつくる提案に直結する──これが、組織を変える力になる。)
組織に広がる学びの連鎖
一人の成功体験がチーム内で共有され、他のメンバーの行動にも波及。営業会議が「学びを連鎖させる場」に変化した。
佐藤の提案事例が営業会議で紹介されたその日、会議室の空気はこれまでとは明らかに違っていた。
数字や納期の確認だけで淡々と進む場が、メンバー同士が身を乗り出して話を聞き合う“共有の場”に変わっていた。
佐藤は緊張した面持ちで口を開いた。
「最初は、ソース仕込みが大変だという話を聞いただけでした。でも、それをどうにかできないかと考えて、開発部と一緒に動いたんです。」
スクリーンには、試作品を持ち込んだ店舗での実演の様子が映し出される。
白いエプロン姿の佐藤が、店長と笑顔で試作品の鍋をかき混ぜている。
「これなら時間が半分で済む」と驚く店長の口元まで、鮮明に映っていた。
話を聞いたベテランの高橋が感心したようにうなずく。
「なるほどな…。俺も先週、アレルギー対応の件を聞いたときに、すぐ提案できるものがないと思って終わらせたけど、部署をまたいで探せば何かできるかもしれないな。」
別の若手も手を挙げた。
「僕も現場で、“衛生管理基準の変更で工程が大変”って話を聞きました。これも商品だけじゃなく、作業効率化の提案ができるんじゃないかと思ってます。」
宮坂はうなずきながら応じた。
「いいですね。聞いた情報は、すぐに終わらせず、他の部門も巻き込んでみる。それが提案の幅を広げる第一歩です。」
すると、隣に座っていた女性営業が「私も…」と小さく声を上げた。
「先週訪問した取引先の担当者が、人件費削減のために仕込みの外注を検討しているって言っていました。もしかしたら、うちの商品やサービスで支援できるかもと思って…。」
会議が終わったあとも、メンバー同士の会話は続いた。
廊下やデスク周りで「あの話、どうなった?」と声を掛け合い、各自が持ち帰った現場の話題が飛び交う。
数か月前までは、こうした情報は個人の頭の中だけに留まり、共有されることはほとんどなかった。
宮坂は、その光景を眺めながら胸の奥で静かに確信した。
(これは“学びの連鎖”だ。一人の成功体験が、他のメンバーを刺激し、行動を変えていく。そしてその変化は、やがて組織全体を動かす力になる。)
宮坂の気づき:変革の本質
組織を変える力は、制度ではなく日常の小さな会話に宿る。営業が顧客の声を持ち帰り、共有し、行動を変えることが文化を形づくっていく。
営業会議を終え、資料を片付けながら宮坂は椅子に深く腰を下ろした。
会議室に残るのは、まだ話し足りなそうなメンバー同士の小さな声と、白板に残ったキーワード。
「困りごと」「現場」「他部門連携」──その文字が、会議中の熱をそのまま映していた。
(組織を変えるって、こういうことなんだな…)
宮坂の胸の中に、ゆっくりと確信が広がっていった。
以前の自分は、組織変革といえば新しい制度や研修プログラム、営業ツールの導入といった“外側からの刺激”ばかりを思い描いていた。
だが、ここ数か月の動きが教えてくれたのは、変革の芽はもっと日常の中にあるということだった。
顧客の現場を知ろうとする一言が、相手の反応を変える。
その情報を持ち帰り、会議で共有することで別のメンバーの行動が変わる。
それがまた新しい提案を生み、成功体験となって次の連鎖を生む。
この循環こそが、組織を少しずつ、しかし確実に変えていく力なのだ。
高橋が会議後に近づいてきた。
「マネジャー、来週は調理工程を改善できる事例をもう少し調べてみます。開発部にも話を通しておきますね。」
その表情は、かつての“価格勝負しかない”という諦めとは別人のようだった。
佐藤もメッセージを送ってきた。
「店長から“ありがとう”って言われました。もっと聞いてみたいことが増えました。」
宮坂は心の中でつぶやく。
(変革の本質は、仕組みや制度だけじゃない。人の意識が変わり、その意識が行動を変え、その行動が文化をつくる。この流れを止めないことだ。)
そして、自分の役割がはっきりと見えた。
それは、現場で芽生えた小さな変化を見逃さず、守り育て、全員に広げていく“媒介者”であり続けることだった。
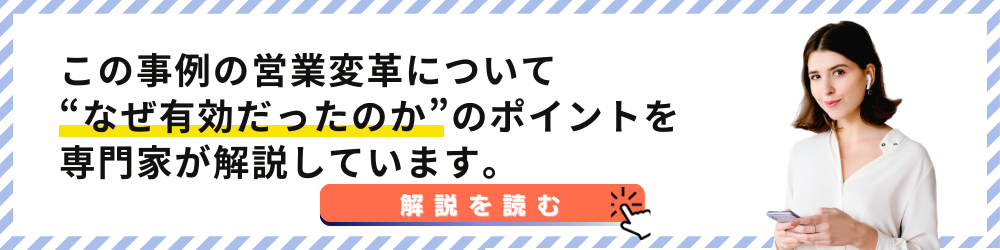
未来への展望
宮坂は“聞く文化”を仕組み化し、越境連携や学習KPIを導入。営業組織が「選ばれる存在」から「頼られる相棒」へと、さらに進化する未来を描いた。
会議室に残ったメモを指でなぞりながら、宮坂は次の3か月の地図を描いていた。
(点を線に、線を面に。個々の成功を、組織の“ふつう”にする。)
まず手をつけたのは、現場情報の循環速度だ。
「聞いた」「持ち帰った」「共有した」が一週間後では遅い。そこで、毎朝10分の“現場スナップ”を始めることにした。前日の訪問で拾った一言・一枚・一数値(顧客の言葉/現場写真/簡易指標)をSlackに投稿し、昼の時間に宮坂が2行の所感を返す。
宮坂「“仕込みに90分”の一言は重い。工程のどこで時間が溶けるか、5W1Hで次回ヒアリングを。」
佐藤「了解です。厨房導線と仕込み手順、写真付きで確認してきます。」
次に、越境の定着。部署をまたぐ協業は“たまたま”では続かない。開発・製造・品質保証の各担当と月2回のケースレビューを設定した。営業が持ち帰った現場の断片を、開発は技術の言葉に、製造は供給の言葉に、品質はリスクの言葉に翻訳する。
開発「粘度条件が合えば、同等風味で短縮いけるかも」
製造「ライン切替は夜間なら対応可。原料手配は2週前告知で」
品質「衛生基準変更のスレッド、営業側にも共有しておきたい」
さらに、宮坂は学習KPIを置いた。売上や粗利だけでなく、“対話の質”を測る軽量指標だ。
・顧客の困りごとを名詞化して記録(例:仕込み時間/衛生記録/アレルギー対応)
・会話の深度を0〜2で自己評価(0:表面的、1:背景まで、2:原因仮説まで)
・“次回聞くこと”を1行で宣言し、完了したらリアクションが付く
数字ではない数字が、チームに小さな緊張感と連帯感をもたらした。
「今週は“背景まで”が少ないな」「次回質問の宣言、3件滞留中だ」。可視化されることで、聞く文化は習慣になっていく。
ベテランの高橋が言った。
「昔は“聞く=弱さ”だと思ってた。でも今は、“聞けるやつ”が一番強い。」
若手の井上が笑う。
「聞くって、相手を試すことじゃなくて、一緒に考える入口なんですね。」
宮坂は、顧客共創の最初の型も用意した。A4一枚のシンプルなテンプレートだ。
1.顧客の一言/現場写真
2.困りごとの定義(名詞)
3.影響(時間/コスト/品質)
4.仮説(3つ)
5.次回の検証質問
6.社内で巻き込む相手
会議では完成形の資料より、この“プロト”の密度を評価する。未完成を持ち寄る勇気が、連鎖を生むからだ。
そして宮坂は3つの合図をチームに共有した。
・会議の最初の5分が顧客の声で始まっているか
・商談の最初の5分が価格ではなく現場で始まっているか
・提案の最初の1枚が商品ではなく“困りごと”になっているか
「合図が揃えば、文化は揃う。」そう言って、宮坂はホワイトボードに3つの丸を描いた。
最後に、半年後の景色を言葉にしてみせた。
「私たちは“選ばれる取引先”から、“頼られる相棒”になる。
その変化は、特別なプロジェクトではなく、毎日の10分の会話から始まる。」
メンバーの頷きは、以前よりもゆっくりで、しかし深かった。
根に水が染みていく速度で、組織は変わり始めている。
変革は日常から生まれる
朝礼やSlack投稿など日常の小さな実践が、変革を継続的に進めていく。
営業変革は特別な施策ではなく、日常の会話から始まる。
翌週。月曜の朝礼で、佐藤が手を挙げた。
「店長に“いちばん困っている工程はどこですか”と聞けました。次回、“ソースの煮詰め時間”を計測してもらうお願いもしました。」
拍手が起きる。形式的なものではない、次の行動が浮かぶ種類の拍手だ。
会議後、宮坂は一人、スクリーンに残った昨日の写真を眺めた。熱で白く曇る厨房、タイマーを気にするスタッフ、沸騰する鍋。
(ここに、私たちの“提案の素材”がある。)
商品カタログにも、原価表にも載っていない。しかし、この現場の一瞬こそが、顧客価値の原石だ。
午後、井上からチャットが飛んだ。
井上「衛生管理の新基準、現場の記録フローを紙からタブレットに移す検討が進んでいました。うちの加熱済み商材の活用で記録点数が減らせるか、次回確認します。」
宮坂「良い視点。困りごと→影響→仮説→検証の順番、A4に落として持ち帰って。」
夕方、ベテランの高橋が席に来た。
「マネジャー、来月から“現場同伴デー”を月一でやりませんか。開発と品質も一緒に。口で聞くより、見るほうが早い。」
宮坂は即答した。
「やろう。現場で同じ空気を吸うのが、最短の合意形成だ。」
日常の粒度で、変革は進む。
朝の10分投稿、昼の2行所感、夕方のA4プロト。
小さいが、止まらない。止めない仕掛けにしてあるからだ。
その週の金曜、宮坂はチーム全員に短いメッセージを送った。
「顧客の本音を引き出せない営業組織、最初に変えるべきことは何か。
答えは“聞くことを仕組みにする”でした。
聞くことで、私たちは相手の未来に参加できる。
来週も、最初の5分を現場から始めよう。」
画面に次々と“いいね”が並び、最後に小さなコメントが届いた。
佐藤「“聞く”って怖かったけれど、今は楽しみです。」
宮坂は微笑んだ。
(変革は、今日の会話の中にある。毎日、少しだけ前へ。)
──変革は続く。ここからは、顧客と一緒に描く未来の章だ。
担当者コメント

この事例は架空のストーリーですが、同じような悩みを抱えるお客様は珍しくありません。
営業が顧客の本音を引き出せない、提案が表面的になってしまう──そうした課題は、製造業や情報システム業、サービス業などさまざまな現場で共通して見られます。
私たちは「決まった答え」を押し付けるのではなく、お客様と一緒に課題を整理し、最適な形を探しながら歩んでいきます。これまでにも、異なる業種や職種のお客様とご一緒し、それぞれの状況に寄り添って伴走してきました。
現場で小さな気づきが生まれ、それが変化につながっていく。その瞬間に立ち会えることこそが、私たちにとって大きな喜びです。
あなたの組織でどこから始めるべきか、無料でシナリオをご提示します。(無料相談)