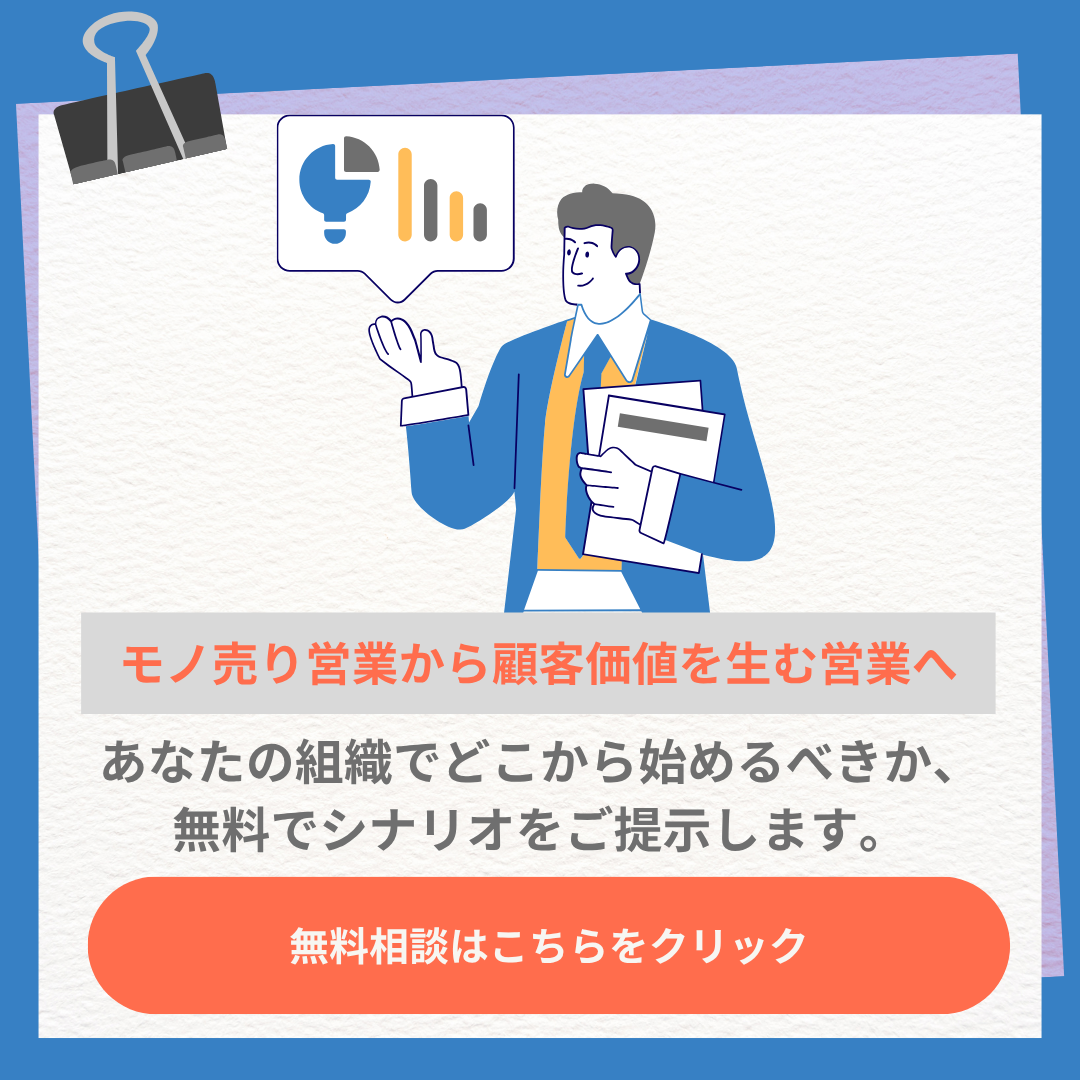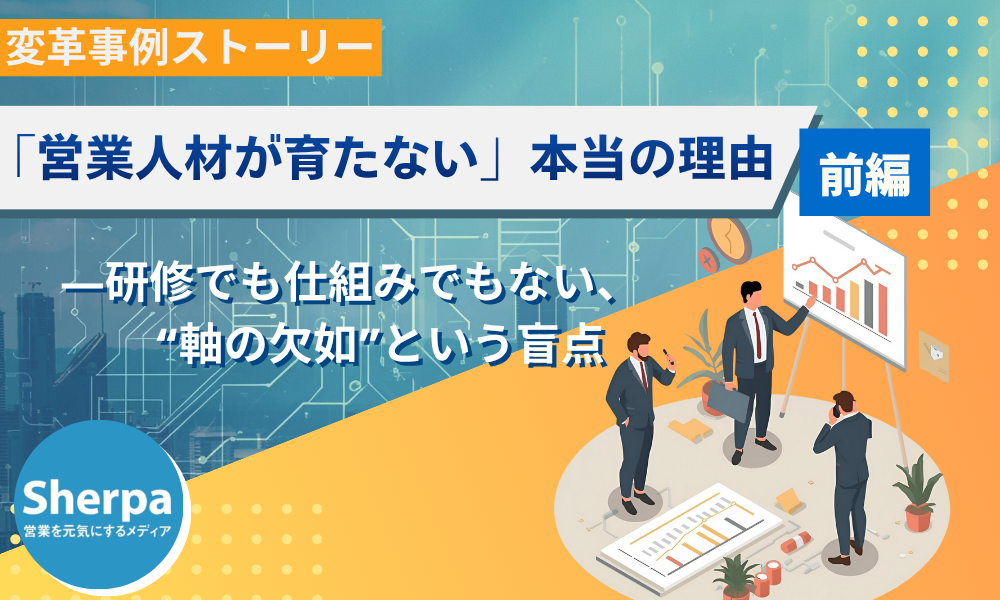
2025.11.11 (更新日:2025.12.04)
営業人材が育たない組織をどう変えるか【前編】
「営業人材が育たない」本当の理由――研修でも仕組みでもない、 “軸の欠如”という盲点
どの企業でも一度は直面するのが、「営業人材が思うように育たない」という課題ではないでしょうか。ベテランの力に頼る一方で、若手は努力を重ねても成果につながらず、マネジャーも育成の手立てを持たない──そんな状況に心当たりはありませんか。研修や施策は実施しているのに、現場には定着せず、数字は伸びない。経営層からは「軸となる人材がいない」という厳しい声が上がる。この記事では、ある電子機器メーカーが直面した現実をもとに、営業企画部が「育成の軸」を模索していくプロセスをお伝えします。
※本記事は、ある企業で実際に行われた営業変革の事例をもとに構成しています。
登場人物や会社名は架空ですが、現場の葛藤、会話、そして変化のプロセスは、すべて実際の出来事から着想を得ています。
主人公
主人公:営業企画部の田中
40歳。営業現場を経験したのち営業企画に異動。これまでに製品知識研修や営業スキル研修を企画・実施してきたが、数字に結びつかない現実に悩んでいる。経営層と現場の板挟みになり、危機感を強く抱いている。
主要登場人物
川村(営業本部長)
52歳。営業部全体を統括する立場。これまでは「エース人材」に支店を任せてきたが、そのモデルが通用しなくなっていることに強い危機感を抱いている。経営会議で「軸となる人材がいない」と強く指摘する。
佐伯(東京支店長)
48歳。営業現場叩き上げ。売上は維持しているが、ベテランに依存していることを自覚。若手を育てる術が分からず、内心では焦りと無力感を抱えている。
安藤(名古屋支店マネジャー)
38歳。プレイングマネジャーとして自身の数字は優秀。しかし部下育成には苦戦し、「どうやってモチベーションを高めればいいのか」と悩む。現場ヒアリングで自ら「育成の軸を持っていなかった」と吐露する。
中村(若手営業)
27歳、入社5年目。顧客訪問は積極的だが成果に結びつかず、「どんな営業を目指せばいいのか分からない」と迷いを口にする。彼女の言葉が営業企画にとって決定的な気づきとなる。
目次
はじめに
フューチャーテック株式会社。産業用センサーや制御機器を主力とする中堅電子機器メーカーである。創業から40年余り、技術力と品質を武器に業界内の地位を築き上げてきた。取引先は大手製造業を中心に広がり、堅実な経営で成長を続けてきた。
表面的には順調に見える。しかし、営業企画に所属する私――田中の目には、数字の裏に潜む危うさがはっきりと映っていた。
毎月、全社の営業データをまとめるのは私の役割である。支店別の売上推移、受注率、案件化の件数、失注理由。それらを眺める時間は、いつも憂鬱だった。
数字そのものはまだ持ちこたえている。しかし、よく見ればその大半を支えているのは限られたベテラン数名。彼らが退けば、次を担う人材が見えない。
「施策は打ってきたはずなのに、なぜ変わらないのか」
胸の奥で問いが繰り返される。私はこれまで、研修という形で営業現場を支えてきた。製品知識を学ばせる集合研修、顧客ヒアリングを想定したロールプレイ、提案スキルを磨くワークショップ。参加者の反応は悪くなかった。終了後には「学びになった」「明日から試したい」といった声が寄せられた。
しかし時間が経つと、その熱は消える。数週間も経てば現場は元のやり方に戻り、成果は数字に反映されない。結局、売上の柱となるのはベテランだけ。若手は迷いながら日々を過ごし、伸び悩んでいる。
その現実を前にして、私は企画担当としての無力さを痛感していた。
一部のベテランに依存しているという現実
売上を支えるのはごく少数のベテラン。若手は努力しても成果が出ず迷走している。自然に育つ時代は終わり、組織の脆さが浮き彫りになっていた。
ある日の午後、営業企画部の定例ミーティング。私は支店ごとのデータを整理したスライドをスクリーンに映し出した。
「ご覧の通り、東京支店は売上の7割を3名のベテランが担っています。名古屋支店も同じ傾向です。若手の数字は横ばい、むしろ下がっている支店もある」
会議室に重い空気が漂う。同僚の一人が、ペンを回しながら口を開いた。
「ベテランが頼りになるのはありがたいけど、彼らもいずれは異動や定年がある。若手が育たないままでは、先が持たない」
別の同僚が続けた。
「行動量は足りているんだよな。訪問件数も提案数も。でも成約率が伸びていない。努力はしてるのに成果が出ないのは、やり方が間違ってるってことだろうか」
私は頷きながらも、答えを返せなかった。若手は顧客訪問を積極的に行い、資料も作成している。しかし、顧客との会話は最終的に価格や納期の話に収束してしまう。結果、提案の価値が伝わらず、競合に負ける。
現場から届く声も、耳に刺さっていた。
「研修で習った質問を使ってみても、お客様は『で、いくら?』と返してくるだけでした」
「自分はどんな営業を目指せばいいのか、正直分からない」
東京支店で聞いた若手営業・中村の言葉は忘れられなかった。彼女は顧客訪問を欠かさず行い、報告書もきちんと提出していた。それでも成果は上がらない。あるとき、支店長の佐伯と一緒に会議室にいた彼女がぽつりとつぶやいた。
「努力しているのに結果が出ないのは、自分が何か根本的に間違っているからなんでしょうか」
佐伯は腕を組み、何も言わずに天井を見上げていた。支店を預かる立場として、若手をどう育てればいいのか答えを持っていない。内心では焦りながらも、指導できない自分への苛立ちを押し隠しているように見えた。
私は心の中でつぶやいた。
──ベテランの背中を見て自然と育つ。そんな時代はもう終わった。
経営会議で突き付けられた本質的な課題
経営層から「軸となる人材不在」という厳しい指摘。研修や施策は場当たり的で定着せず、体系的な育成が必要だと突きつけられた。
月例の経営会議。会議室の空気はいつも以上に張り詰めていた。役員や部門長が並ぶ長机の一角に座る私は、配られた資料に目を落としながら、鼓動の早さを抑えようとしていた。
営業本部長の川村が立ち上がり、支店別の人員構成と業績を映し出した。
「各支店を任せられるコア人材がいない。このままでは危うい」
会議室が静まり返った。川村の声には苛立ちが滲んでいた。プロジェクターに映し出されたグラフは、ベテランの名前が突出して並び、若手の数字は低迷している。
役員の一人が私に視線を向けた。
「田中、営業企画として研修も施策もやってきたはずだ。それでも成果が出ていないのはなぜだ?」
全員の目がこちらに注がれる。背中に汗が滲むのを感じた。私はしばし沈黙した後、言葉を絞り出した。
「研修直後には手応えがあります。しかし、現場に戻ると従来のやり方に戻ってしまう。仕組みとして定着していないのです」
別の役員が厳しい口調で言い放った。
「要は、その場しのぎなんだ。エースが自然に育つ時代は終わった。体系的に育てなければ未来はない」
その言葉は鋭く胸に刺さった。私は研修やツール提供で十分だとどこかで思っていた。しかしそれは「点」でしかなく、組織に「線」としてつながる仕組みがなければ意味がない。
川村が最後に言った。
「育成の仕組みを持たなければ、会社の未来は描けない。田中、君たち営業企画がどう動くかにかかっている」
私は無言で頷いた。自責の念と同時に、これまでの考えを根底から覆された感覚があった。

打ち手を探しても見つからないもどかしさ
過去の施策は一見効果的に見えるが、線につながらず、成果が持続しない。営業企画部には無力感が広がり、新しい打ち手が見えない。
経営会議から数日後、営業企画部の会議室にメンバーが集まった。長机には資料が積まれ、スクリーンには支店別の数字が映し出されている。テーマは明確だった。「次世代の営業人材をどう育てるか」。
田中は冒頭で切り出した。
「これまで私たちは、研修やツール導入で現場を支援してきました。しかし、成果は数字に現れていません。つまり、施策は“点”でしかなく、線になっていないのです」
沈黙のあと、同僚の一人が口を開いた。
「でも、アンケート結果は悪くなかったはずだ。『実践したい』『役立つ』という声も多かった。じゃあ、なぜ定着しない?」
別のメンバーがすぐに言葉を継いだ。
「現場任せになっているんだろう。東京支店ではマネジャー次第でOJTのやり方が全然違う。熱心に付き合う人もいれば、『自分で学べ』と放り出す人もいる」
田中は心の中でうなずいた。確かに、数字やアンケートには現れない“温度差”がそこにあった。支店ごと、マネジャーごとに取り組みの質はばらつき、体系性がない。
議論は堂々巡りになった。
「もっと実践型研修を増やすべきじゃないか」
「いや、既にやってきた。それでも結果は同じだ」
「ツールで進捗を見える化したらどうだ」
「手間が増えるし、見える化しても、行動が変わらなければ意味がない」
机上には過去5年の研修履歴がずらりと並んでいた。製品知識、提案スキル、商談ロールプレイ。確かに一つ一つは効果的に思える。参加者は一定の満足を示し、アンケートには前向きな言葉が並んでいた。だが積み上げても「仕組み」にはならず、現場で持続する変化を生み出してはいなかった。
田中はため息をついた。
「結局、この会社には“育てる仕組み”がないんだよ。点を打ち続けているだけで、線につながっていない」
その言葉に会議室の空気が重くなった。誰も反論はしなかった。皆、同じ思いを抱いていたからだ。施策の“在庫”は尽きている。新しい打ち手は見当たらない。数字の表情が示す未来の脆さを前に、営業企画の無力感が広がっていった。
育成の軸がないことへの気づき
若手は「どんな営業を目指すのか」が分からず迷い、マネジャーも育成方法を持たない。経営層は危機感を抱える。すべての根本は「育成の軸」の欠如だと気づく。
突破口を求めて、田中は現場ヒアリングに出た。まず訪れたのは東京支店。支店長の佐伯と数名の若手営業が会議室に集まった。テーブルの上には案件資料や活動報告が並んでいたが、空気はどこか重かった。
田中は切り出した。
「現場で一番困っていることを、率直に教えてください」
一瞬沈黙が走った。誰も口を開こうとしない。やがて若手の中村が、勇気を振り絞るように口を開いた。
「私たち、どんな営業を目指せばいいんでしょうか」
その場の空気が一変した。佐伯が驚いた顔で問い返す。
「どういう意味だ?」
中村は俯きながら続けた。
「訪問件数は増やしています。提案資料も作っています。でも成果につながらない。数字だけを追っていても、自分が何を目指す営業なのかが分からないんです」
言葉は震えていたが、その目には必死さが宿っていた。会議室にいた若手の数名も静かにうなずいていた。
その声を受け、佐伯はしばらく黙っていた。やがて苦しげに吐き出した。
「…正直に言うと、私もどう育てればいいのか分からない。昔は背中を見せれば自然と育った。でも今は違う。経験則では導けないんだ」
支店長のその言葉には、自責と無力感がにじんでいた。会議室に残った沈黙は、答えのない問いを突き付けていた。
翌週、田中は名古屋支店を訪れた。マネジャーの安藤と面談した際、彼は椅子に深く腰を沈め、疲れた表情で語り始めた。
「自分の数字を作るのは得意です。でも、部下をどう育てればいいのかとなると、正直何も持っていなかった。自分のやり方を真似すればいいとしか思っていなかった」
その声は低く、どこか悔しさを帯びていた。数字を出す力があるからこそ、育成で無力な自分を痛感しているのだろう。
帰りの新幹線。窓の外を流れる街の灯りを眺めながら、田中はノートを開き、言葉を殴り書きした。
──若手は目指す像が分からず迷っている。
──マネジャーは育て方を持たず、数字に追われている。
──経営層は「軸となる人材の不在」という現実に危機感を募らせている。
すべてが一つにつながった。
「何を目指して育てるのか」が曖昧なままでは、未来は描けない。
田中はようやく気づいた。
──育成の“軸”をつくらなければ、この会社の未来は変わらない。
それはスローガンではなく、「顧客の未来を共に描ける営業とは何か」「その姿に近づくために、どんな経験を積ませるか」。
育成体系を貫く“軸”、つまり、育成を設計するうえでの方針と基準を明確にすることだった。
しかし、軸を掲げるだけでは人は変わらない。どんなに良い理念でも、現場で使えなければ意味がない。
田中は考えた。
「この“軸”を、どうやって育成やマネジメントの中で機能させるか」
──必要なのは、現場と経営をつなぎ、共通言語として浸透させる方法だ。
その夜、田中はパソコンの画面を閉じ、ノートを開いた。
「理想の営業像」「行動プロセス」「成長ステップ」…浮かんだ言葉を並べながら、点が線になる構造を探していった。
こうして、後に全社を巻き込むことになる育成体系構築プロジェクトの構想が動き出した。
まだ答えは見えていない。だが、確信に近い感覚は持ち始めていた。
“研修や制度の導入”だけでは変わらない。
育成の軸を定めること、それが変革を起こすための最初の一歩だった。
まとめ ― 未来を描くための第一歩
点の施策ではなく、線でつながる育成体系が必要と確信。会社として人財育成の軸が必要であると変革の原点に立った。いうここから営業企画部による「育成体系構築」の挑戦が始まる。
経営会議で突き付けられた現実。
現場ヒアリングで聞いた若手の迷い。
そして、マネジャー自身の無力感。
田中は一つの確信にたどり着いた。
「育成の軸がなければ、支店を支える人材は育たない」
これまで点でしかなかった研修や施策を、線につなげる仕組みへと変えなければならない。単発の研修ではなく、組織全体で人を育てる体系をつくらなければ未来は描けないのだ。
その夜、田中は営業企画部の仲間と長く議論を続けた。
「営業ビジョンを体現できる人材像とは何か」
「その姿に向けて、どんな経験を積ませるべきか」
「現場が納得し、共に歩める仕組みはどうあるべきか」
答えはまだ見えない。だが、会社全体で「育成の軸」をつくり上げることこそが、組織変革の唯一の道であることははっきりしていた。
ここから、フューチャーテックの営業企画部による「育成体系構築」の挑戦が始まる。
後編では、実際の育成体系構築の過程で浮かび上がった営業組織の本質的な課題、全社展開によって現場に生まれた変化と未来への展望を描いています。
担当者コメント
この事例は架空の事例ストーリーですが、同じような悩みを抱えるお客様は珍しくありません。
営業が顧客の本音を引き出せない、提案が表面的になってしまう──そうした課題は、製造業や情報システム業、サービス業などさまざまな現場で共通して見られます。
私たちは「決まった答え」を押し付けるのではなく、お客様と一緒に課題を整理し、最適な形を探しながら歩んでいきます。これまでにも、異なる業種や職種のお客様とご一緒し、それぞれの状況に寄り添って伴走してきました。

自社のありたい姿を落とし込む、営業育成体系
あなたの組織ではどこから始めるべきか、無料でシナリオをご提示します。