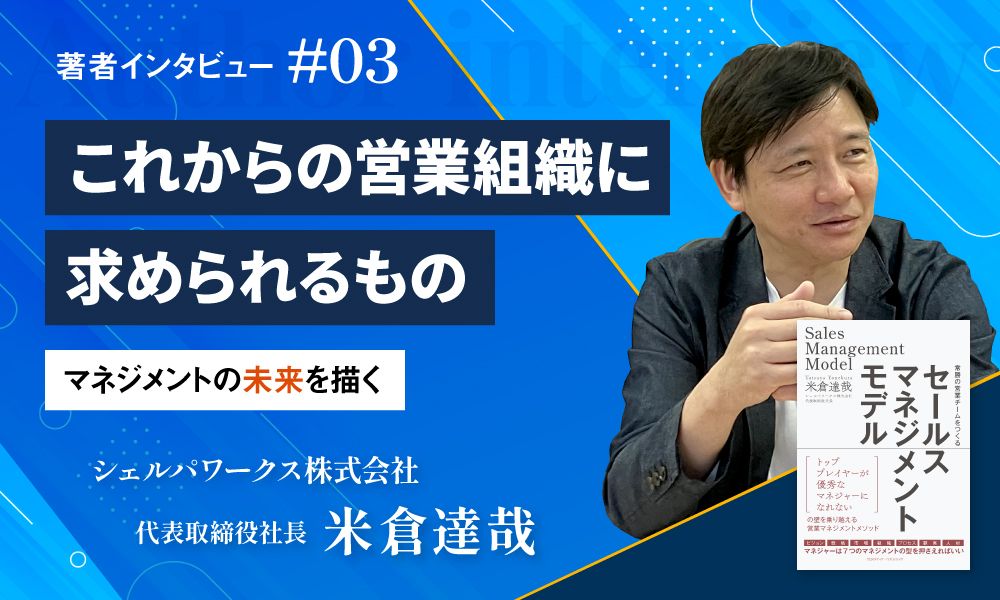
2025.05.16 (更新日:2025.09.25)
著者インタビュー|第3回【これからの営業組織に求められるもの】
―マネジメントの未来を描く
『セールスマネジメントモデル』の著者であり、シェルパワークス株式会社 代表取締役社長として営業改革に取り組む米倉達哉氏をお迎えした対談も今回が最終回。最終回では、急速に多様化する市場と組織環境の中で、画一的な管理から脱却しつつ、共通のビジョンを軸に個々の特性を最大限に引き出す手法を探ります。
▶関連記事:対談 第1回「営業という仕事の本質に立ち返る――環境変化に立ち向かうために必要なこと」はコチラ
▶関連記事:対談 第2回「営業現場を変えるには何が必要か――組織で成果を生み出す「型」を考える」はコチラ
目次
画一性と多様性を両立させるマネジメントへ
- ここまで、営業マネジメントに求められる「型」や、現場を支える体系づくりについて伺ってきました。ここからは、さらに視野を広げて、これからの営業組織、営業マネジメントの未来について伺いたいと思います。
まず、米倉さんは今、営業マネジメントにどんな変化が求められていると感じていますか?
米倉
そうですね。大きく言うと、「個の力を束ねるマネジメント」から「多様な力を引き出すマネジメント」への転換だと考えています。今は、個々人の強みや特性が多様化している。時代や市場の変化が早く、顧客ニーズも複雑化している中で、営業組織も画一的な育成や管理だけでは通用しない。営業マネジメントは“体系化された基準に基づいてしくみで徹底する”という話をしてきましたので、矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、今後はこれを基盤として、この基盤の上に多様な個を載せていくイメージです。画一性と多様性をいかに同居させ、それをどう束ね、活かしていくか――そこにマネジメントの力が問われていくと思います。
- 多様性を前提にしたマネジメントですね。確かに、すべてにおいて「全員同じやり方で」というのは、難しい時代になっているのかもしれません。
米倉
はい。さらに言えば、多様な個を「尊重する」だけではなく、「共通の方向に向かわせる」ことが大事だと思っています。だから、ビジョンや共通基準はこれまで以上に重要になります。個々人が自分らしく動くのはいいけれど、組織として一体感がなければ、バラバラに動いてしまう。
ただ誤解してほしくないのは、「個の尊重」や「多様性を尊重」というと、どうしても画一性を軽視してしまいがちですが、そうなると、属人的なチームに戻ってしまいます。重要なのは、「守破離(しゅはり)」という考え方になります。
- 守破離ですか?
米倉
はい、「守破離(しゅはり)」とは、茶道や剣道などの修行における3つの段階を指す言葉です。守は師の教えを忠実に守り、破はそれを発展させ、離は独自の道を切り開く段階です。営業チームもこれと同じ考えで、先ずは、体系化された基準に基づいて決めたことを徹底させるというベースを創り上げることです。そして、それができるようになってから、個々の多様性を活かしてチームとしての新たなスタイルを築きあげていくというイメージです。方向性と裁量、その両方をバランス良くマネジメントできるか――これがこれからの営業マネジメントに求められる力だと考えています。
成果を生むのは「対話を通じた共通理解」
- 「方向性と裁量のバランスを取る」ですか。すごく難易度が高そうですが、具体的にはどういう力が求められるのでしょうか?
米倉
まず必要なのは、「抽象と具体を行き来できる力」だと思います。現場に寄り添いながらも、単なる個別対応に終始せず、常に全体のビジョンや戦略を意識する。そしてもう一つは、「対話を通じて共通理解を作る力」です。一方的な指示命令ではなく、メンバーそれぞれと対話しながら、「なぜこれを目指すのか」を共有していく。この対話型マネジメントができるかどうかで、組織の質は大きく変わってくると感じています。
- 営業マネジャーに求められる役割も、ますます高度化しているのですね。
米倉
そう思います。マネジメントの役割は、単なる進捗管理ではない。チーム全体が自己成長し続ける環境を作ること、メンバーの可能性を引き出すこと、組織として市場に適応し続けること。こうした複雑な要素を扱いながら、現場で成果を出していく。とても難しいですが、だからこそ、マネジメントの質が組織の未来を左右すると言えるのだと思います。
マネジャーの学びが、組織の変化をつくる
- そんな中で、これからの営業マネジャーが特に意識すべきことは何でしょうか?
米倉
私も偉そうなことは言えませんが、一つ挙げるなら、「学び続ける姿勢」ですね。これだけ環境が変化する中で、過去の成功体験だけに頼るのは危険です。むしろ、自分自身も常に学び、成長し続ける存在であること。それがメンバーにもポジティブな影響を与えますし、組織としての変化適応力にもつながります。営業マネジャーも、「自分は完成していない」という前提で、学び続けることを楽しめる人が、これからの時代にはより求められるのだと思います。
- 確かに、マネジャー自身が「学び手」であり続ける姿は、チームにとっても大きな支えになりますね。
米倉
はい。組織の成長は、マネジャーの成長に比例すると考えています。そして、マネジャーが学び続ける姿勢を見せることで、メンバーも自然と変わっていきます。営業マネジメントというのは、結局のところ「人の成長をどう支えるか」という営みなのだと思います。その本質を見失わずに、これからも向き合う人材を増やしたいですね。
セールスイネーブルメントは“仕組みで支える力”
- 米倉さん自身は今後どのようなテーマに注目していますか?
米倉
これからは、単に営業スキルを高める支援にとどまらず、営業組織全体の「成果を出し続ける仕組み」を作る支援――いわゆるセールスイネーブルメントにも、さらに力を入れていきたいと考えています。個人の頑張りに依存するのではなく、組織として、誰もが成長し、成果を上げられる環境を整えていく。そのために、営業マネジャーの育成はもちろん、プロセスや仕組みづくりまで一緒に伴走していきたいと思っています。
- これからの営業組織にとって心強い存在ですね。
米倉
そうありたいですね。孤独の中でも必死にチームを導こうとしている営業マネジャーたちに寄り添い、共に未来を描き、共に歩んでいく。そんな支援をこれからも追求していきたい。営業という仕事が再び社会に元気を取り戻す、その一翼を担えたらと願っています。
- 最後に、これから営業マネジメントに取り組もうとしている方々に向けて、メッセージをお願いします。
米倉
営業マネジメントは、決して楽な仕事ではありません。でも、やりがいはものすごく大きい仕事だと思っています。チームが成長し、メンバーが成長し、お客様に貢献できる喜びを共有できた時の感動は、何ものにも代えがたいものがあります。変化の激しい時代ですが、営業マネジメントの本質は変わらないと考えています。人と組織の可能性を信じて、学び続け、支え続ける。この姿勢を持ち続けることが、未来を切り拓く力になると信じています。ぜひ一緒に、これからの営業組織を作っていきましょう。
- いろいろなお話を聞くことができました。ありがとうございました。
米倉
ありがとうございました。
▶第1回:営業という仕事の本質に立ち返る――環境変化に立ち向かうために必要なこと
▶第2回:営業現場を変えるには何が必要か――組織で成果を生み出す「型」を考える
【プロフィール】

シェルパワークス株式会社
代表取締役社長 米倉達哉
1970年1月31日生まれ。兵庫県伊丹市出身。大学卒業後、海外添乗をするために大手旅行会社に入社。法人営業として企業と官公庁を担当し、営業の基本を叩き込まれる。その傍ら、サッカー観戦ツアーなども企画し、7年間で海外50都市以上を添乗。2000年に営業力強化支援をするために富士ゼロックス総合教育研究所 (現パーソル総合研究所)に入社。米国流セールスサイエンスメソッドを活用して、営業の戦略実行コンサルティングを展開。2016年に日本の営業を元気にするためにシェルパワークス株式会社を設立し、代表取締役に就任。これまでに300を超える営業変革プロジェクトを牽引。
