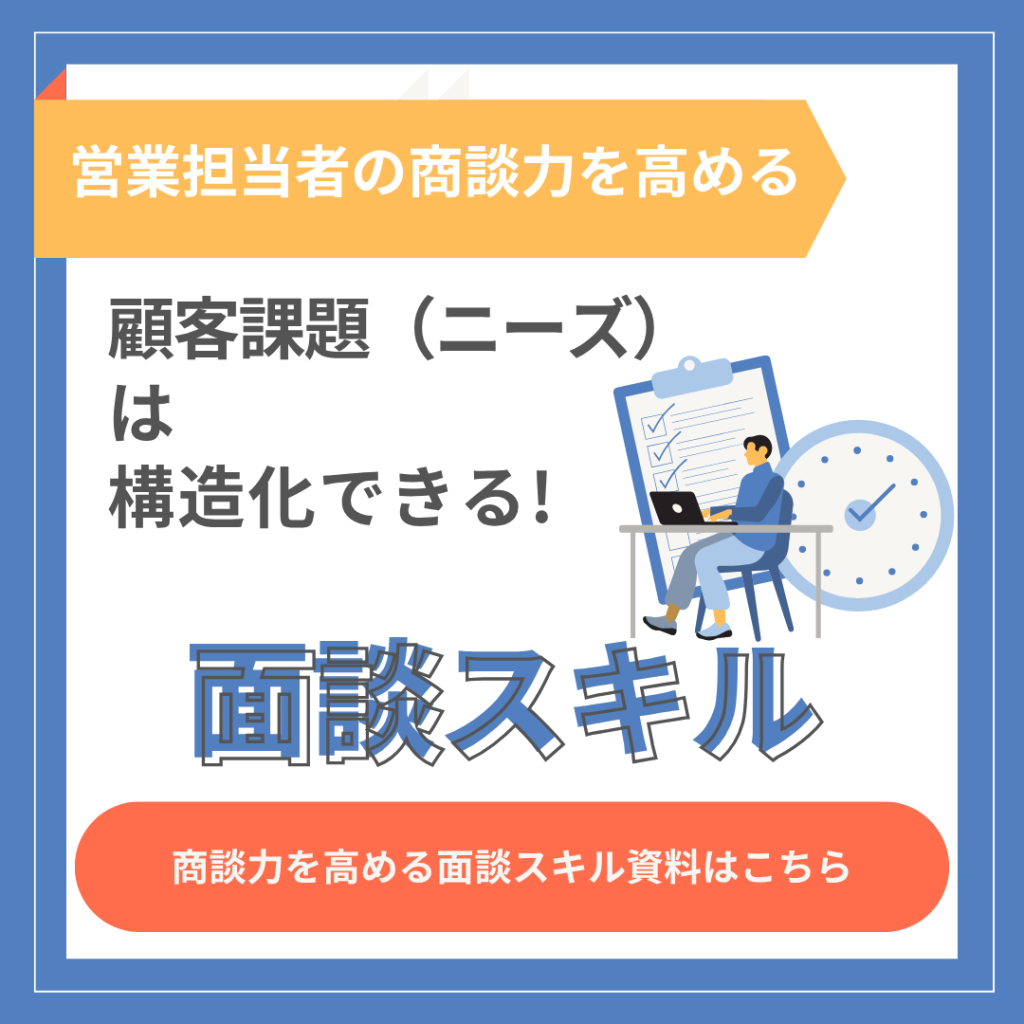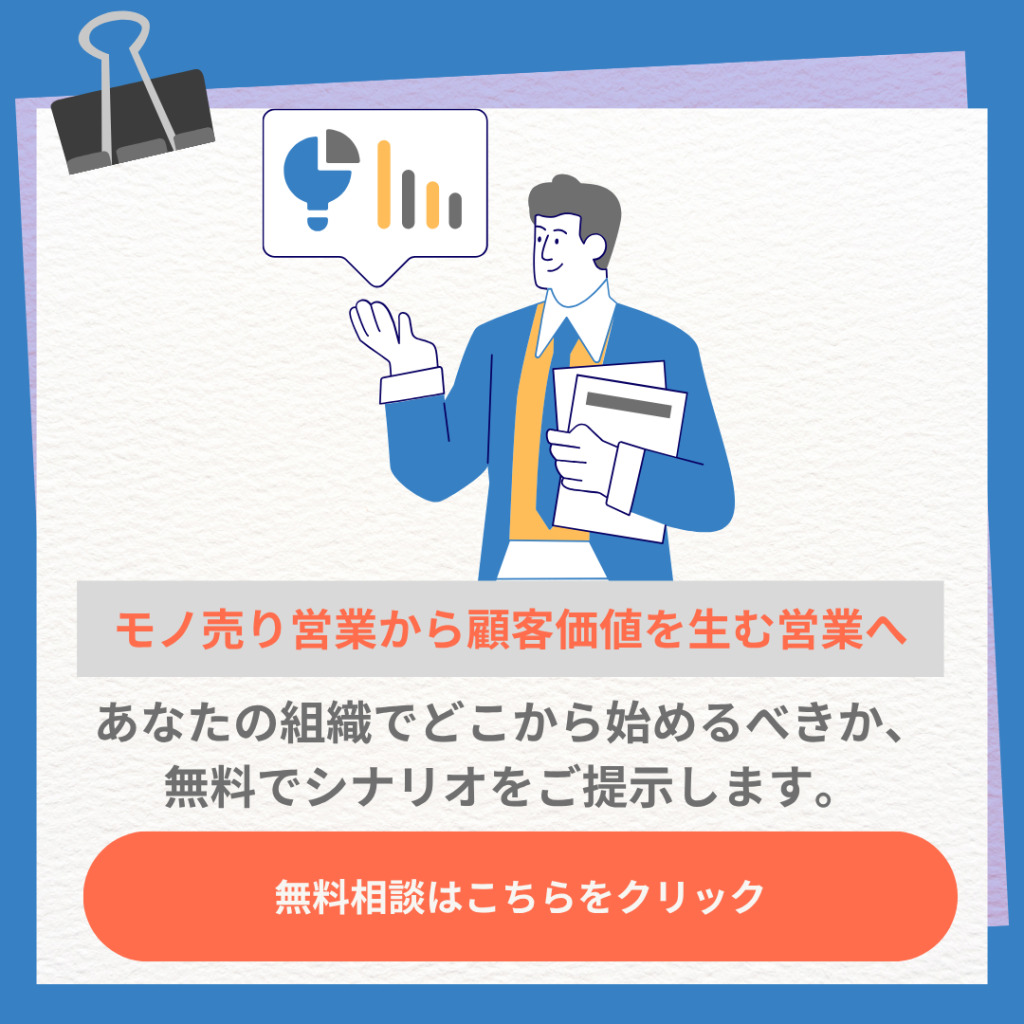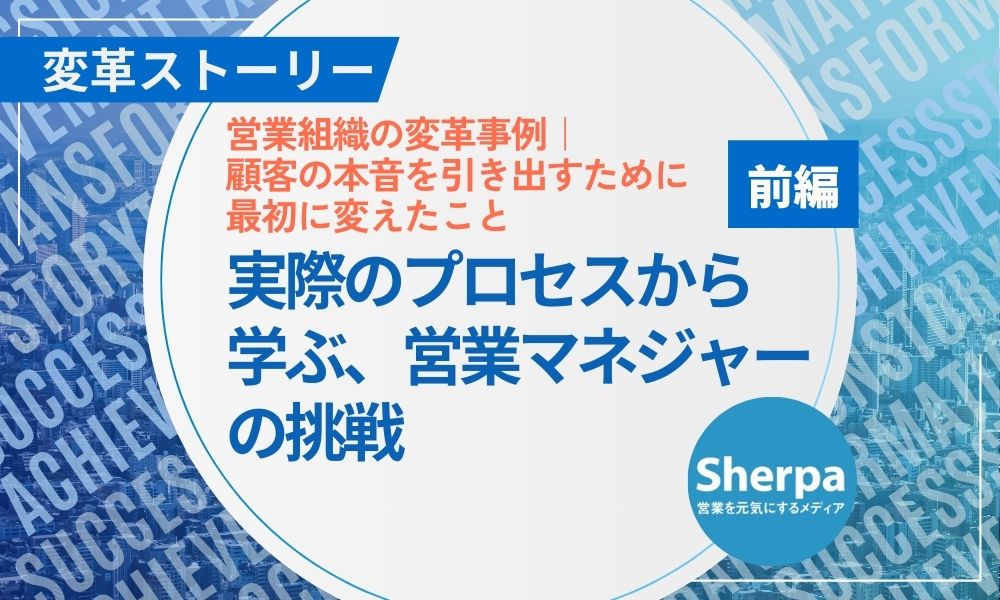
2025.09.17 (更新日:2025.10.16)
顧客の本音を引き出すために最初に変えたこと【前編】~実際のプロセスから学ぶ、営業マネジャーの挑戦~
営業組織が顧客の本音を引き出せず、価格交渉ばかりに終始してしまう──。本記事では老舗食品メーカーの営業チームが変革に踏み出した事例をもとに、営業会議や1on1面談を通じて“顧客と向き合う文化”を育てたプロセスを紹介します。
(注意)本記事は、ある企業で実際に行われた営業変革の事例をもとに構成しています。登場人物や会社名は架空ですが、現場の葛藤、会話、そして変化のプロセスは、すべて実際の出来事から着想を得ています。
目次
変化の波にさらされる老舗メーカー
顧客課題が「価格交渉」から「事業存続・事業戦略」へと変化し、営業組織は“モノ売り”からの変革を迫られていた。
桜井フードサービスは創業70年を超える業務用食品メーカーだ。学校給食から社員食堂、外食チェーン、惣菜工場まで、多様な顧客に原料や調味料を届けてきた。
派手な広告もなく、堅実な営業活動と品質の安定で信頼を積み重ねてきた会社。だが、その“安定”に少しずつヒビが入り始めていた。
「人が集まらない」
「原材料コストが上がりすぎる」
「消費者の好みが変わりすぎて、次の一手が見えない」
近年、顧客から届く言葉は、かつての「もっと安く」「味を良くしてほしい」といった商品改良や価格交渉だけではなくなっていた。課題は複雑さを増し、事業の存続や戦略に関わる深刻なテーマへと移っていた。
宮坂は、その変化を肌で感じていた。数字上は安定しているが、このままでは顧客との距離は開く一方だ。顧客が求めているのは、商品や値下げの提案だけではない──それは間違いなかった。
宮坂マネジャーの危機感 ― 営業会議が形骸化する理由
宮坂は、営業マネジャーとして7名のメンバーを束ねている。若手とベテランが混在するチームは、一見するとバランスが良く、数字も大きく崩れてはいない。
しかし、宮坂の胸の奥には、常に薄い不安が張り付いていた。
社内会議では「現状維持」を評価される。経営陣からも「安定している部署」と言われる。だが、心のどこかで思う。
(この“安定”は、成長の停滞と表裏一体じゃないのか…?)
その疑念が決定的な形になったのは、大手外食チェーン本社での打ち合わせだった。桜井フードが長年取引してきた、重要顧客のひとつだ。
新商品の紹介も終わり、価格条件もまとまった頃、社長がふとこんな言葉を口にした。
「桜井さんの商品はいい。でも、私たちが本当に欲しいのは“モノ”じゃない。
一緒に未来を考えてくれるパートナーなんです。」
その瞬間、宮坂の胸に小さな棘が刺さったような感覚が走った。
帰りの電車。窓に映る自分の顔をぼんやりと見つめる。
(俺たちは、本当に顧客の未来を考えているだろうか…?)
(商品の話ばかりで、相手が抱える経営課題や現場の悩みに踏み込めていないんじゃないか…?)
数日後、別の顧客先で似たような場面があった。
中堅惣菜メーカーの購買担当が、商談の途中でため息交じりに言った。
「最近、どこの取引先も似たような提案しか持ってこないんですよね。うちの状況や課題を本気で考えてくれる会社は少ないです。」
その言葉を聞いた瞬間、宮坂は確信した。
顧客が本当に求めているのは、安くて良い商品ではない。課題解決を一緒に考える姿勢だ。
現場の現実 ― 若手・ベテラン営業が顧客に踏み込めない背景
若手営業は質問スキル不足、ベテラン営業は価格交渉への依存により、営業組織全体が顧客理解に踏み込めていなかった。
その確信を胸に、宮坂はチームの現場をもう一度見直すことにした。
口頭で聞くだけでは分からない。商談に同行し、肌で感じるしかない。
最初に同行したのは、入社3年目の若手営業・佐藤だった。
目的地は地方都市のファミリーレストランチェーン本部。会議室に通され、佐藤は丁寧にカタログを広げた。
「こちらが今度発売になる減塩タイプのソースです。風味はそのままに塩分を15%カットしています。価格は…」
担当バイヤーは一応うなずくが、表情は動かない。
「ふーん、悪くないけど、今は原価を下げたいんだよね。」
佐藤はわずかに間を置き、カタログの別ページを開いた。
「では、こちらの既存品であれば…」
会話は性能と価格のやり取りだけで終わり、バイヤーの表情に興味の色は最後まで戻らなかった。
別の日、今度はベテランの高橋と訪問した。
相手は長年の取引先である給食事業者の購買担当。商談が始まるなり、担当は単刀直入に切り出した。
「来期の予算が厳しくてね。少しでも単価を下げてほしい。」
高橋は慣れた口調で答える。
「分かりました。社内で検討してみます。」
それ以上のやり取りはなく、話は終了した。
宮坂は心の中でつぶやく。
(どうして“なぜ予算が厳しいのか”を聞かない? 背景が分かれば別の提案もできるはずなのに…)
数件の商談を回ったあと、宮坂の中で言葉が浮かんだ。
「顧客の現場や状況を知ろうとする会話が、ほとんどない。」
若手は「何を聞けばいいか分からない」と戸惑い、ベテランは「価格勝負が現実」と半ば諦めていた。
そして営業会議は数字報告と詰問で終わり、新しいアイデアや学びが生まれることはほぼない。
そんな現状を象徴するような会話が、同行から戻った日の夕方にあった。
宮坂がデスクで資料を整理していると、佐藤が申し訳なさそうに声をかけてきた。
「マネジャー…やっぱり、お客様の困りごとを聞きたいんです。でも、どこから切り出せばいいか分からなくて…。」
宮坂は一瞬返す言葉を探し、ゆっくりとうなずいた。
(これが、今のうちの営業の姿か…。まずはここを変えないといけない。)
営業が顧客の本音を引き出せない理由
営業が“話すこと”に偏り、顧客課題を聞き出す文化や情報共有の仕組みが欠けていたことが、営業組織変革を阻む要因だった。
数日間の商談同行を終えた宮坂は、自席の前でしばらく立ち尽くしていた。
手帳にはびっしりとメモが残っている。顧客の要望、会話の断片、そして自分が見た光景。
しかし、それらを読み返すたびに、胸の奥に重いものが沈んでいく感覚があった。
デスクに腰を下ろし、宮坂は手帳を開いた。
そこには、いくつもの共通するパターンが見えていた。
・若手営業は「何を聞けばよいのか分からない」と感じ、質問が浅く終わる
・ベテランは「価格勝負が現実だ」と諦め、値下げ交渉で会話を閉じてしまう
・営業会議は数字報告と詰問で終わり、学びや新しい提案が生まれない
ページをめくるたびに、同じ構図が繰り返されていることに気づく。 翌日の朝礼。
宮坂はあえて昨日の訪問で感じたことをチームに話してみた
宮坂:「お客様はどんな表情をしていた?」
若手:「最初は聞いてくれるんですが、途中から反応がなくなって……」
宮坂:「何か困っていることを聞けたか?」
若手:「聞きたいんですが、どこから聞いていいのか分からなくて」
「佐藤の商談では、減塩ソースの説明から始まって、そのまま価格の話で終わってしまった。
高橋の商談では、相手から“単価を下げてほしい”と言われて、それ以上の会話がなかった。」
話を聞くメンバーは真剣な表情をしているが、その目には「でも仕方がない」という諦めが滲んでいた。
ベテランの一人が口を開く。
「マネジャー、もちろん本当は色々聞きたいですよ。でも、向こうが値段の話しかしないと、それ以上は…」
若手の佐藤も続ける。
「僕も聞きたいんです。でも、何から切り出せばいいか分からなくて…話が途切れちゃうんです。」
宮坂は深くうなずいた。
(これはスキルの話ではない。営業としての“姿勢”や“目的”が、もう顧客との間に壁を作ってしまっている。)
心の中でそう確信した瞬間、背筋に冷たいものが走った。
このままでは、いくら商品力があっても、顧客との関係は表面的なままで終わってしまう。
「顧客の本音を引き出せない営業組織」という現実が、はっきりと目の前に形を持ったのだ。
さらに宮坂は、社内での会議の様子を思い返した。
数字の報告、目標との差異、対策の確認。
「次回はもっと訪問件数を増やそう」
「新商品の提案数を伸ばそう」
そんなやりとりが、毎月のように繰り返されている。
だが、その中に「顧客の声をどう拾ったか」という話はほとんど出てこない。
たまに出ても、「こんな要望があった」程度の一方通行な報告で終わる。
掘り下げられず、共有されず、結局は個人の中で消えてしまっている。
この現実を、どうすれば変えられるのか。
宮坂はホワイトボードに太字で一行書いた。
「なぜ顧客の本音が聞けないのか?」
その下に、自分なりに考えた仮説を書き出していく。
1.営業が「聞く」ことより「話す」ことに重点を置いている
2.顧客との会話のゴールを「受注」に置きすぎている
3.現場で得た情報を共有する仕組みがなく、組織として学習できていない
文字にしてみると、問題はより鮮明になった。
これは個々の力量ではなく、組織の文化の問題だ。
(もしこの文化を変えられたら──)
宮坂の脳裏に、一つのイメージが浮かんだ。
顧客の現場で自然に質問が生まれ、商談後にその情報が会議で共有され、他の営業が次の訪問で活かす。
そんな循環ができれば、組織は確実に強くなるはずだ。
だが同時に、簡単ではないことも分かっていた。
長年染みついた営業スタイルは、そう簡単には変わらない。
宮坂はペンを置き、窓の外に視線を移した。
空は曇っていたが、その奥に少しだけ青空が覗いている。
(最初の一手は、きっと派手なことじゃなくていい。日常の中で、少しずつ“聞く文化”を育てるところからだ。)
心の中でそう呟くと、机の上の手帳を閉じた。
ここから先は、マネジャーとしての決断と行動の番だった。
最初に変えるべきこと
営業組織変革の第一歩は、大改革ではなく1on1面談で顧客との対話を振り返り、営業スキルと意識を育てることだった。
「顧客の本音を引き出せない理由」を整理した宮坂は、すぐにでも打ち手を打ちたかった。
だが同時に、自分に言い聞かせる。
(大きな改革をいきなりやっても、現場はついてこない。最初は、小さくても確実に“変化の芽”を作ることだ。)
そこで宮坂が選んだのは、1on1面談の導入だった。
週に一度、メンバーと一対一で向き合う時間をつくる。
会話のテーマは数字や進捗ではなく、「顧客とのやりとりで感じたこと」や「印象に残った一言」だ。
初回、席に呼ばれた若手の佐藤は、やや緊張した面持ちで椅子に腰を下ろした。
「じゃあ、今日の商談で何か印象に残ったことは?」と宮坂が尋ねると、佐藤はしばらく考えてこう答えた。
「…お客様が“今は原価を下げたい”と言っていました。でも、そこからどう話を広げればいいか分からなくて…。」
宮坂はうなずき、「それを聞いてどう感じた?」と重ねた。
佐藤は少し考え、「たぶん、現場が何か困っているんだろうなとは思いました」と答えた。
そこから二人は、どうすればその“困りごと”を自然に聞き出せるかを一緒に考えた。
ベテランの高橋との1on1では、別の課題が浮かび上がった。
「正直、価格勝負は避けられないと思っている。でも、それじゃ組織は強くならないことも分かってるんだ。」
宮坂は頷きながら、「じゃあ、価格以外で話せるネタを増やすには何ができそうか?」と投げかける。
高橋は少し沈黙した後、「現場の課題をもう少し知れば、違う提案ができるかもしれないな」と口にした。
1on1は回を重ねるごとに、メンバーが少しずつ自分の体験や気づきを語る場へと変わっていった。
最初は「特にありません」と短く終わっていた会話も、今では10分、15分と続くことが増えてきた。
宮坂は感じていた。
(こうして少しずつ、顧客の現場に興味を持つ意識が芽生えていく。これが組織を変える最初の一歩になるはずだ。)
この事例の営業変革について、“なぜ有効だったのか”のポイントを専門家が解説しています。
こちらから無料でダウンロードできます。
営業会議の変革へ
数字中心だった営業会議を“顧客の現場の声”から始める仕組みに変えることで、営業組織は本音に基づく提案力を高め始めた。
1on1で少しずつ変化の兆しが見え始めた頃、宮坂は次の一手を決めていた。
(この“顧客の現場に興味を持つ姿勢”を、チーム全体で共有できる場を作ろう。)
そのために、営業会議の冒頭を大きく変えることにした。
数字報告から始めるのをやめ、「顧客の現場の声」から会議をスタートするのだ。
初回の会議、メンバーが席につき、いつものように資料を開こうとした瞬間、スクリーンに映し出されたのは売上グラフではなかった。
写真だった。
人手不足で忙しそうに動き回る、顧客店舗の厨房の様子だ。
薄暗いバックヤードで、額に汗をにじませながら鍋をかき混ぜるスタッフの表情が映っている。
「この現場に行ったのは誰?」宮坂が問いかけると、若手の佐藤が手を挙げた。
「僕です。店長から“人が足りなくて限界”って言われました。」
「そのとき、どう返した?」
「…言葉が出なくて、商品の話に戻してしまいました。」
「どう返せたらよかったと思う?」
「“一緒に考えます”って言えたらよかったです。」
このやり取りをきっかけに、他のメンバーも口を開き始めた。
「先週訪問した工場でも、現場責任者が人員不足の悩みを話してくれました。」
「原価高騰でメニューを変えざるを得ない、という飲食店もありました。」
会議室に漂っていた数字中心の緊張感が、少しずつ“共有”の空気へと変わっていくのを宮坂は感じた。
(これだ。現場のリアルな声を共有することで、数字の裏にある意味が見えてくる。)
「営業組織変革で最初にやるべきことは?」問いへの答え
営業組織を変革する鍵は、顧客の現場を共有し、営業チーム全体で顧客の本音を起点に学び合う文化をつくることだった。
顧客の本音を引き出せない営業組織、最初に変えるべきことは何か──。
数週間にわたる商談同行、1on1面談、そして営業会議の改革を経て、宮坂はようやくその答えにたどり着いた。
「顧客の現場を共有し、そこから会話を生み出す場をつくること」。
これまでの営業会議は、数字を確認し、差異を詰めるだけの場だった。
数字が良ければ安心し、悪ければ原因を追及する。
そこに“顧客の姿”はほとんど存在していなかった。
だが、会議の冒頭で顧客現場の写真を映し、実際の会話を共有するようになってから、数字の裏にある意味が見え始めた。
「なぜ売上が下がったのか」ではなく、「現場で何が起きているのか」という視点が芽生えたのだ。
会議を終えた後、若手の佐藤が宮坂に声をかけてきた。
「マネジャー、来週は店長に“何が一番困っていますか”って聞いてみようと思います。」
その表情には、不安と同時にわずかな自信が混じっていた。
別のメンバーも、「工場の責任者ともう少し雑談して、作業の様子を見せてもらおうと思う」と話してくれた。
これまでなら価格や納期の話で終わっていたやり取りが、現場に踏み込む一歩に変わろうとしている。
宮坂は感じていた。
スキル研修や新しいツールの導入も必要だろう。
しかしそれらは、“顧客に関心を持つ文化”という土壌がなければ根付かない。
顧客の現場を知ろうとする姿勢。
その姿勢を共有し、互いに学び合う場。
この二つが揃って初めて、組織は顧客の本音を引き出せるようになる。
会議室を出て行くメンバーたちの背中を見送りながら、宮坂は小さく息をついた。
(ここからが本当のスタートだ。小さな芽を、組織全体の文化に育てていく。)
この小さな変化は、やがて現場での行動を変え、想像もしなかった成果を生み出すことになる──。
後編では、営業組織が「顧客と共創する仕組み」をどのように構築したのかを紹介します。
あなたの組織ではどこから始めるべきか、無料でシナリオをご提示します。