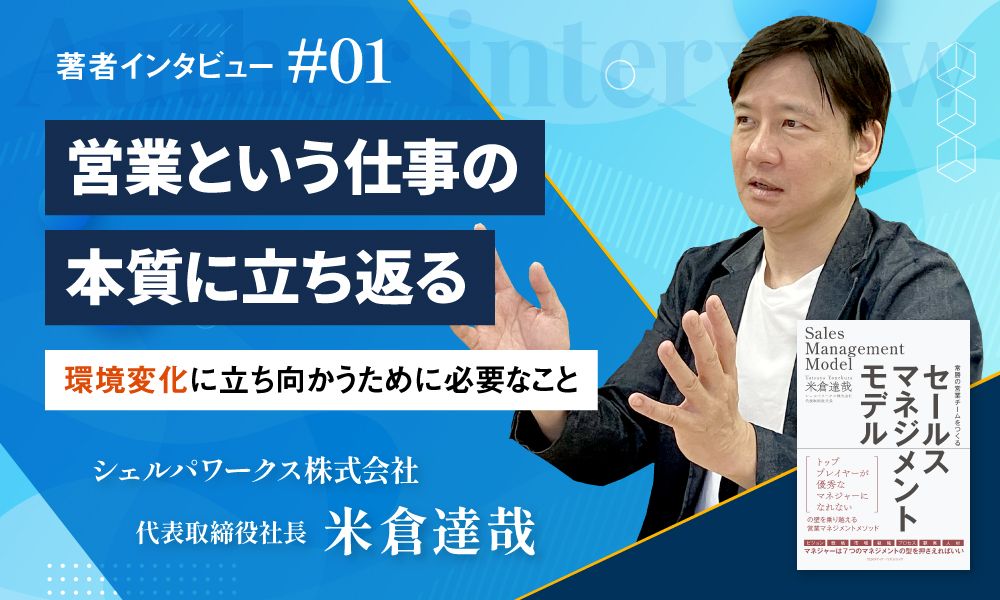
2025.05.16 (更新日:2025.09.25)
著者インタビュー|第1回【営業という仕事の本質に立ち返る】
―環境変化に立ち向かうために必要なこと
今回は、『セールスマネジメントモデル』の著者であり、シェルパワークス株式会社の代表取締役社長として営業改革に取り組む米倉達哉氏をお迎えし、全3回にわたる対談をお届けします。変化の激しい市場環境において、営業組織が直面する課題の本質や、現場力を底上げする「型」の構築ポイントを深掘りし、実践にすぐ活かせる示唆をお伝えします。
第1回は「営業という仕事の本質に立ち返る――環境変化に立ち向かうために必要なこと」をテーマに、営業の原点や執筆に至った問題意識を紐解きます。
目次
営業の現場から、静かに元気が失われている
- 米倉社長はこれまで長く営業の世界に携わってこられたんですよね?
米倉
はい、新卒で営業職に就き、以降ずっと営業の世界に携わってきました。卒業後は海外に行きたいという思いが強く、そのために旅行会社に入社しました。法人営業として企業と官公庁を担当し、そこで営業の基本を叩き込まれました。その後、営業力強化支援をするために富士ゼロックス総合教育研究所(現パーソル総合研究所)に入社しました。以来、20年以上にわたり、営業力強化や営業人材育成に携わってきました。
- 営業の世界に長くいる米倉社長が今回、この書籍を執筆するに至った背景について聞かせていただけますか?

米倉
営業という仕事は、苦しいことも多いですが、その先にある喜びが非常に大きい仕事です。企業と企業、人と人をつなぐ、社会にとってなくてはならない存在だと思っています。ただここ数年、現場の営業たちに元気がなくなってきているのを感じるようになりました。努力しても成果に結びつかない、報われにくくなっている。そんな現実を目の当たりにして、「このままではいけない」という強い危機感を感じていました。
そうした現実に向き合い、営業の元気を取り戻すきっかけを作りたい――そんな思いが今回の執筆につながりました。
「頑張れば何とかなる」では通用しない時代へ
- 「営業の元気がなくなっている」という点について、もう少し詳しく教えていただけますか?
米倉
はい。以前は、日本経済そのものが右肩上がりで、頑張ればそれなりに成果が出る環境がありました。しかし、バブル崩壊以降、経済は縮小局面に入り、営業の世界も「頑張れば何とかなる」という時代ではなくなりました。さらに、リーマンショック、コロナ禍を経て、市場はますます厳しくなっています。お客様も情報を豊富に持つようになり、営業に求められるレベルが高度化・複雑化しました。加えて、人材不足の問題も深刻化し、1人当たりの生産性向上が強く求められるようになっています。そうするとマネジャーもメンバーも余裕がなくなってくるんですよね。特に、マネジャーは数字のプレッシャーを受けてメンバーに対しても、ついつい結果ばかりを追求することに目が向いてしまう。そうした環境が、営業の現場から元気を奪っていると感じています。
- 営業パーソンや営業マネジャーにとっては厳しい時代ですね。
米倉
そうですね。ただ、現場の営業もマネジャーも、それぞれが真摯に仕事に向き合っています。誰一人として怠けているわけではありません。目の前のお客様からは高いレベルの要求や細かいコンプライアンス、社内ルールへの対応を迫られます。そして、細かく丁寧に社内調整も含めて対応しています。ただ、これだけ努力しても成果につながらないことが増えてきており、その状況がさらなる疲弊を生んで、現場は慢性疲労症候群になっていく。つまり、個人の頑張りだけではもう限界が来ている、ということなんだと思います。この現実を変えるためには、頑張り方そのものを変えていく必要があると考えています。
- 「頑張っているのに報われない」というのは、とても切実な課題ですね。
米倉
はい。本当に切実な課題だと感じます。
- 努力だけではどうにもならない壁がある――そんな感覚でしょうか。
米倉
そうだと思います。かつては、頑張れば何とかなる時代でした。でも今は、頑張るだけでは成果に結びつかない。むしろ、頑張り方を間違えると、徒労感ばかりが積み重なり、現場のモチベーションが下がってしまう。その現状を変えるには、営業組織そのもののあり方を見直す必要があると感じました。
マネジメントこそが営業を変える起点になる
ー現場の状況を変えるには、まずどこから手を付けるべきでしょうか?

米倉
私は「営業マネジメントの変革」だと考えました。営業の最前線で、戦略を実行に移し、メンバーを導き、お客様との信頼関係を築く――その中心にいるのがマネジャーです。
しかし今、そのマネジャーたち自身が過重な負担を抱え、疲弊しています。案件対応に追われ、育成にも十分に時間が割けない。こうした現場では、組織全体の底上げは望めません。
だからこそ、営業マネジャーを支える「型」を整備し、彼らがチーム全体を導きやすくする仕組みが必要だと強く思うようになりました。
- 確かに、マネジャーが疲弊してしまっては、チーム全体も元気になれませんね。
米倉
おっしゃる通りです。マネジャーは単なる上司ではなく、組織の現場を動かす推進役です。マネジャーが元気になれば、現場も元気になる。逆に、マネジャーが疲弊していれば、どんなに素晴らしい戦略も絵に描いた餅になってしまいます。
- つまり、営業マネジメントの変革が、現場の元気にもつながるというわけですね。
米倉
はい。その通りです。
- 具体的に、営業マネジメントにおいてどんな課題が多いと感じていますか?
米倉
一番は、「全体感を持てていない」ことですね。目の前の案件対応やメンバー指導に追われ、組織全体をどう動かすかという視点が抜け落ちてしまう。たとえば、サッカーのチームを考えてみてください。個々の選手がどんなにうまくても、フォーメーションや戦術がなければ試合には勝てません。営業も同じです。個々の頑張りに頼るだけでは限界がある。組織としてどう勝つか、その全体設計が必要です。
個の努力を成果につなげる“仕組み”が必要だ
- 非常にわかりやすい例えですね。では、全体感を持つためには何が必要でしょうか?
米倉
必要なのは、「体系」と「基準」を明確にして、それをしくみで「徹底」することです。まずは、営業プロセスを体系化し、それぞれのフェーズで求める行動と成果を定義する。そして、それを基準としてチームに共有する。何ができると次のステージに進めるのか、そのために特に効果的なアクションが何か、それはどのレベルの質を伴って行うべきなのか、これらを属人的に任せるのではなく、体系的に全員が共通認識として持つ。そして、認識するだけでなく、それを確実に遂行するための仕組みを回す。こうした仕組みがないと、現場はどうしても場当たり的な判断に頼らざるを得なくなり、再現性のある成果が生まれにくくなります。
繰り返しになりますが、まずは成果につながるプロセスを体系化し、それに基づく基準を明確に設定する。そして、メンバー一人ひとりがその基準を理解し、実践できる状態を作る。これができれば、組織として安定的に成果を出せるようになります。
- つまり、営業マネジメントも「個人の頑張り」から「組織の仕組み」へと転換する必要があるわけですね。
米倉
はい。個人の努力は大前提として必要です。ただ、属人的なやり方だけでは組織全体を強くできない。努力は高い確率で成果につながっていかないといけません。だからこそ、努力を成果につなげやすくする「型」を整備することが重要だと思っています。それができれば、マネジャーの負担も減り、チーム全体の底上げにもつながる。営業が再び元気を取り戻すためには、この「型化」が欠かせないと感じています。
▶第2回:営業現場を変えるには何が必要か――組織で成果を生み出す「型」を考える
【プロフィール】

シェルパワークス株式会社
代表取締役社長 米倉達哉
1970年1月31日生まれ。兵庫県伊丹市出身。大学卒業後、海外添乗をするために大手旅行会社に入社。法人営業として企業と官公庁を担当し、営業の基本を叩き込まれる。その傍ら、サッカー観戦ツアーなども企画し、7年間で海外50都市以上を添乗。2000年に営業力強化支援をするために富士ゼロックス総合教育研究所(現パーソル総合研究所)に入社。米国流セールスサイエンスメソッドを活用して、営業の戦略実行コンサルティングを展開。2016年に日本の営業を元気にするためにシェルパワークス株式会社を設立し、代表取締役に就任。これまでに300を超える営業変革プロジェクトを牽引。
